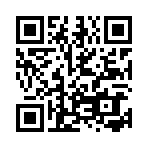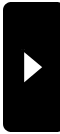◆労働相談◆
Tel.077-527-8575 Fax.077-521-2534
Email : fukuhosg@email.plala.or.jp
福島県の保育士の実態調査の報告会&要請行動
5/12日、福島市内で「東日本大震災以降の福島県の保育士と学童保育指導員の労働と意識に関する調査」報告会を開催しました。調査を実施したのは、全国福祉保育労働組合と立命館大学石倉研究室。調査の回答では、9割が福島で働きたい、と回答。しかし実態は、放射能測定や親への対応、屋内の保育プログラムの作成など新たに業務が増加し、また自分の生活や子どもの健康、先が見通せないことへの不安など、たくさんの問題や悩みがあることがわかりました。およそ3割の保育士が仕事への意欲低下を訴え、他にも健康悪化、ストレスなども訴えています。こうした現状に対し、政府が何ら手立てを取っていないことが問題です。
翌13日は、実行委員会のメンバーが、福島県庁で記者会見、多くの記者が熱心に聞き取り質問をしていました。午後は市内にある復興庁に要請。調査から分かる実態を説明し、復興庁としての対応を求めました。担当者は、「健康問題はすぐに厚生労働省に伝える。保育士の増員についてはもう少し詳しいデータがないと取り上げられない」と回答しました。被災地の出先機関である復興庁担当者があまりに被災地の実態を知らず、1歩引いた態度であったことに出席者からは「復興庁は一体何を支援してくれるところなのか」と厳しい声もあがりました。
被災地で働く選択をした人が、そこで住み続けることは権利です。福島でもどこでも、労働者にも子どもにも等しく権利は保障されるべきでね。
復興も事故の収束もまだまだ遠いのが現実です。今、政府が進めようとしている企業参入の促進や保育士定数の規制緩和、新システムによる直接契約制の導入などは、ますます被災地の労働者を苦しめる結果をもたらします。私たちがしなければならないことは、権利としての保育・福祉を守る、そのための声を広げていくことではないでしょうか。



〔産経新聞に掲載された記事〕 福島の保育関係者 震災後、心身とも疲弊 仕事続けたいが意欲低下 2013.5.14 01:59
東日本大震災後も福島で仕事を続けたいが、意欲は低下している-。保育関係者を対象に、立命館大大学院の石倉康次研究室が行った調査で、こんな実態が明らかになった。保育関係者の9割は県内で働くことを望んでいるが、同時に震災に伴うストレスを今も感じているという。同研究室は近く、国に対して保育現場の労働条件の改善などを要請する。
調査は昨年12月から今年1月にかけ、県内354カ所の保育所や学童保育所と、保育関係者を対象に実施(回収率は33・9%)された。原発事故後、「引き続き現地で保育を続けたい」と答えた人は9割に達し、「検討中」「できれば移転したい」(どちらも1・7%)を大きく上回った。
労働実態は悪化しており、「震災後、仕事が増えた」と答えた人は62・5%。その仕事内容は「放射線量の計測」が93・3%と最も多かった。9割近くの保育関係者が震災に伴うストレスを今も抱え、肩こりや首こりに悩まされ、睡眠不足に陥っていた。「仕事への意欲の低下」は震災直後よりも高まっていることも分かった。
健康状態には「地域差」がうかがえる。福島第1原発に近い浜通りほど「ストレスを実感する」割合が高かった。労働条件の改善点として「賃金の改善」と「必要な職員数の確保」はどちらも7割を超え、「休日の確保」も3割に上った。
石倉教授は「保育士らは子供を守る最前線にいることを実感した。しかし、それにふさわしいサポートが得られず心身両面で限界に近づいている。福島で職員を募集しても来ないような状況は、子供を守る職務への意欲の低下という事態を招いてしまっている」と指摘している。
翌13日は、実行委員会のメンバーが、福島県庁で記者会見、多くの記者が熱心に聞き取り質問をしていました。午後は市内にある復興庁に要請。調査から分かる実態を説明し、復興庁としての対応を求めました。担当者は、「健康問題はすぐに厚生労働省に伝える。保育士の増員についてはもう少し詳しいデータがないと取り上げられない」と回答しました。被災地の出先機関である復興庁担当者があまりに被災地の実態を知らず、1歩引いた態度であったことに出席者からは「復興庁は一体何を支援してくれるところなのか」と厳しい声もあがりました。
被災地で働く選択をした人が、そこで住み続けることは権利です。福島でもどこでも、労働者にも子どもにも等しく権利は保障されるべきでね。
復興も事故の収束もまだまだ遠いのが現実です。今、政府が進めようとしている企業参入の促進や保育士定数の規制緩和、新システムによる直接契約制の導入などは、ますます被災地の労働者を苦しめる結果をもたらします。私たちがしなければならないことは、権利としての保育・福祉を守る、そのための声を広げていくことではないでしょうか。
〔産経新聞に掲載された記事〕 福島の保育関係者 震災後、心身とも疲弊 仕事続けたいが意欲低下 2013.5.14 01:59
東日本大震災後も福島で仕事を続けたいが、意欲は低下している-。保育関係者を対象に、立命館大大学院の石倉康次研究室が行った調査で、こんな実態が明らかになった。保育関係者の9割は県内で働くことを望んでいるが、同時に震災に伴うストレスを今も感じているという。同研究室は近く、国に対して保育現場の労働条件の改善などを要請する。
調査は昨年12月から今年1月にかけ、県内354カ所の保育所や学童保育所と、保育関係者を対象に実施(回収率は33・9%)された。原発事故後、「引き続き現地で保育を続けたい」と答えた人は9割に達し、「検討中」「できれば移転したい」(どちらも1・7%)を大きく上回った。
労働実態は悪化しており、「震災後、仕事が増えた」と答えた人は62・5%。その仕事内容は「放射線量の計測」が93・3%と最も多かった。9割近くの保育関係者が震災に伴うストレスを今も抱え、肩こりや首こりに悩まされ、睡眠不足に陥っていた。「仕事への意欲の低下」は震災直後よりも高まっていることも分かった。
健康状態には「地域差」がうかがえる。福島第1原発に近い浜通りほど「ストレスを実感する」割合が高かった。労働条件の改善点として「賃金の改善」と「必要な職員数の確保」はどちらも7割を超え、「休日の確保」も3割に上った。
石倉教授は「保育士らは子供を守る最前線にいることを実感した。しかし、それにふさわしいサポートが得られず心身両面で限界に近づいている。福島で職員を募集しても来ないような状況は、子供を守る職務への意欲の低下という事態を招いてしまっている」と指摘している。