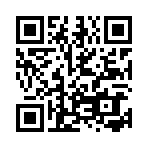◆労働相談◆
Tel.077-527-8575 Fax.077-521-2534
Email : fukuhosg@email.plala.or.jp
春闘本番! 40年前の腰痛闘争に学ぶ
1973年に、福祉保育労滋賀支部の前身である日社労組(日本社会福祉事業職員労働組合)滋賀支部は、当時のびわこ学園で深刻な問題になっていた職員の腰痛を改善するために大幅職員増を求めて国を動かす運動をしています。支部では、当時の支部執行委員長であった田中浩蔵氏を招き、春闘学習会を開催しました。

退職者が4人に1人、夜勤は月16回
田中氏によれば、当時のびわこ学園は、不十分な制度の下で利用者数や介護負担が増えるなかで、職員の健康破壊が進み、次々と倒れる状態にありました。労働組合は人員増を理事会に要求し改善もさせてきましたが、職員の身体的精神的疲労が極限に達するなかで(1970年前半には職員の毎日加療率が47%、退職者が25%、欠員補充ができないため夜勤が月16回という深刻な状態)、労組は理事会に対し、ストライキも辞さない構えで事態の改善を求め9回に渡り団体交渉を重ねてきました。そこで組合の要求の正しさと経営の怠慢を明らかにしつつ、要求を実現するためには制度改善による財源確保が必要不可欠と認識します。そのなかで理事会から「職員の健康を守るために、園児1/3を退園させたい」との提案がされました。

退園児はひとりも出させない
それに対し労組は「退園児はひとりも出させない」と内部のたたかいから、県や国に働きかけ、共闘を広げる運動へと進んでいきます。県担当課と交渉を重ね、さらに知事室前に座り込み、知事との直接面談を実現し、また国会でも取り上げられ、当時の田中角栄首相が「重症児施設の予算拡充を検討する」と言明したことなどから事態は収拾していきます。結果、翌年に制度が改善され、1975年には職員1.1:利用者1という職員配置が実現し、職員25名増という大幅な人員増が実現します。こうした運動を通じて、現在に続く制度改善と要求を実現し、職員の健康と利用者の生活を守ってきました。今にも共通する課題が多くあり、私たちの活動に生かすべきことは少なくありません。

深い連帯と協同が国を動かした
田中氏は、「腰痛闘争は労働条件闘争であったが、内実は親の会、理事会、労働組合が、それぞれの立場で運動を展開しつつ、お互いの立場を認めつつ、その主軸に重症児の主体的に生きる願いを社会的に訴えていこうという基本的一致があった」とし、「この深いところでの連帯、協同が国の施策を動かした」とまとめています。
その力になったものは、何より「労働組合員の団結」であり、交渉や粘り強い対話を通じて得た理事会や親の会との「認識の一致への確信」、そして労組や関係団体の「心強い連帯」、国民の多くが支持しているという「合意が形成」されたことにあります。
1960年代後半~70年代前半にかけての、びわこ学園の腰痛闘争は、現在も福祉職場の労働組合運動を続ける私たちにっとって、多くの教訓を得ることができる貴重な歴史です。
退職者が4人に1人、夜勤は月16回
田中氏によれば、当時のびわこ学園は、不十分な制度の下で利用者数や介護負担が増えるなかで、職員の健康破壊が進み、次々と倒れる状態にありました。労働組合は人員増を理事会に要求し改善もさせてきましたが、職員の身体的精神的疲労が極限に達するなかで(1970年前半には職員の毎日加療率が47%、退職者が25%、欠員補充ができないため夜勤が月16回という深刻な状態)、労組は理事会に対し、ストライキも辞さない構えで事態の改善を求め9回に渡り団体交渉を重ねてきました。そこで組合の要求の正しさと経営の怠慢を明らかにしつつ、要求を実現するためには制度改善による財源確保が必要不可欠と認識します。そのなかで理事会から「職員の健康を守るために、園児1/3を退園させたい」との提案がされました。
退園児はひとりも出させない
それに対し労組は「退園児はひとりも出させない」と内部のたたかいから、県や国に働きかけ、共闘を広げる運動へと進んでいきます。県担当課と交渉を重ね、さらに知事室前に座り込み、知事との直接面談を実現し、また国会でも取り上げられ、当時の田中角栄首相が「重症児施設の予算拡充を検討する」と言明したことなどから事態は収拾していきます。結果、翌年に制度が改善され、1975年には職員1.1:利用者1という職員配置が実現し、職員25名増という大幅な人員増が実現します。こうした運動を通じて、現在に続く制度改善と要求を実現し、職員の健康と利用者の生活を守ってきました。今にも共通する課題が多くあり、私たちの活動に生かすべきことは少なくありません。
深い連帯と協同が国を動かした
田中氏は、「腰痛闘争は労働条件闘争であったが、内実は親の会、理事会、労働組合が、それぞれの立場で運動を展開しつつ、お互いの立場を認めつつ、その主軸に重症児の主体的に生きる願いを社会的に訴えていこうという基本的一致があった」とし、「この深いところでの連帯、協同が国の施策を動かした」とまとめています。
その力になったものは、何より「労働組合員の団結」であり、交渉や粘り強い対話を通じて得た理事会や親の会との「認識の一致への確信」、そして労組や関係団体の「心強い連帯」、国民の多くが支持しているという「合意が形成」されたことにあります。
1960年代後半~70年代前半にかけての、びわこ学園の腰痛闘争は、現在も福祉職場の労働組合運動を続ける私たちにっとって、多くの教訓を得ることができる貴重な歴史です。
2016年02月24日 Posted by 福祉保育労組滋賀支部 at 13:57 │Comments(0) │福祉保育労組 奮闘日記
「市民の会しが」結成へ 戦争法廃止のために野党は共闘を!
滋賀県で、戦争法の廃止を実現するために、多くの市民が力を合わせる団体が結成されます。
「安保法制廃止と立憲主義の回復を求める市民の会しが」は、県内で戦争法(安保法制)に反対し、成立後も廃止を目指して活動してきた団体、個人が呼びかけ人となり、結成の準備を進めてきました。
結成後は、戦争法廃止の宣伝や行動を続けながら、参議院選挙やそれに続く国政選挙で、戦争法を配廃止し憲法を守る勢力を拡大するために野党に共闘を呼びかけていきます。福祉保育労も参加する「滋賀県憲法共同センター」の代表も呼びかけ人の一員となっています。
結成集会は、2月20日(土)14時~ 草津アミカホール 詳しくは⇒ http://shiminnokaishiga.wix.com/home


「安保法制廃止と立憲主義の回復を求める市民の会しが」は、県内で戦争法(安保法制)に反対し、成立後も廃止を目指して活動してきた団体、個人が呼びかけ人となり、結成の準備を進めてきました。
結成後は、戦争法廃止の宣伝や行動を続けながら、参議院選挙やそれに続く国政選挙で、戦争法を配廃止し憲法を守る勢力を拡大するために野党に共闘を呼びかけていきます。福祉保育労も参加する「滋賀県憲法共同センター」の代表も呼びかけ人の一員となっています。
結成集会は、2月20日(土)14時~ 草津アミカホール 詳しくは⇒ http://shiminnokaishiga.wix.com/home


2016年02月16日 Posted by 福祉保育労組滋賀支部 at 13:15 │Comments(0) │お知らせ│憲法が生きる平和な社会へ
障害者団体が滋賀県知事部局に要請
障害者の生活と権利を守る滋賀県連絡協議会(障滋協)は、10日、滋賀県知事部局と障害者施策に関する要請を行いました。
障害当事者をはじめ、家族、NPO役員、労働組合(福祉保育労)、養護学校教員など障害者福祉に関わる参加者が、精神障害者の公共交通機関の利用助成や入所施設やグループホームの整備、職員の処遇改善・加配、障害児教育の期間延長など、県に対し施策の拡充を訴えました。

なかでも、重度障害者の生活の問題では、県内では施設やグループホームが不足し、岡山県や福井県の施設に入所せざるを得ない実態があり、さらに驚くべきことには、県がグループホーム新設の申請をしても、国から6~7割しか認められていない事実が明らかになったことです。国の社会保障予算の削減は障害者分野で特に厳しく、その影響がこうした問題を生んでいます。
参加した家族からは「湖北地域に重度障害者を対象にした施設(入所)をつくってほしい」「入院したら親は24時間つきっきりになる。もう限界だ」「重度障害者の地域生活をどうするのか、ちゃんと考えてほしい」と切実な訴えが続きました。
国は総合支援法3年目の見直しを行っていますが、施策の拡充どころか、いっそうの予算縮小が進められる危険もあります。県は独自に対策を講じる責任がありますし、また国に対して県民の声を届け、施策の改善を求めていくべきです。
障害当事者をはじめ、家族、NPO役員、労働組合(福祉保育労)、養護学校教員など障害者福祉に関わる参加者が、精神障害者の公共交通機関の利用助成や入所施設やグループホームの整備、職員の処遇改善・加配、障害児教育の期間延長など、県に対し施策の拡充を訴えました。
なかでも、重度障害者の生活の問題では、県内では施設やグループホームが不足し、岡山県や福井県の施設に入所せざるを得ない実態があり、さらに驚くべきことには、県がグループホーム新設の申請をしても、国から6~7割しか認められていない事実が明らかになったことです。国の社会保障予算の削減は障害者分野で特に厳しく、その影響がこうした問題を生んでいます。
参加した家族からは「湖北地域に重度障害者を対象にした施設(入所)をつくってほしい」「入院したら親は24時間つきっきりになる。もう限界だ」「重度障害者の地域生活をどうするのか、ちゃんと考えてほしい」と切実な訴えが続きました。
国は総合支援法3年目の見直しを行っていますが、施策の拡充どころか、いっそうの予算縮小が進められる危険もあります。県は独自に対策を講じる責任がありますし、また国に対して県民の声を届け、施策の改善を求めていくべきです。
2016年02月10日 Posted by 福祉保育労組滋賀支部 at 13:53 │Comments(0) │福祉・保育・介護情報
野洲市が独自対象の生活困窮者支援の条例制定へ
2月2日付の京都新聞が、滋賀県野洲市の生活困窮者支援の条例制定への動きについて報じています。
野洲市では、これまでも生活困窮者の自立支援に取り組んでいて、昨年4月に国の生活困窮者自立支援法実施を受けて、独自に社会的孤立など困窮者の範囲を広げ、市のネットワークで早期に発見・支援を行おうというものです。
国の生活困窮者自立支援法は、生活困窮者や社会的孤立者を伴走しながら自立にむけた支援を行う積極面と、半面、生活保護が必要な人まで受給しずらくなるのではという問題も指摘されています。
野洲市の条例は「早期発見」に重きを起き、自立支援につながていこうというものです。こうした動きが、国の施策の拡充につながるといいですね。
京都新聞記事 ⇒ http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20160202000024

野洲市では、これまでも生活困窮者の自立支援に取り組んでいて、昨年4月に国の生活困窮者自立支援法実施を受けて、独自に社会的孤立など困窮者の範囲を広げ、市のネットワークで早期に発見・支援を行おうというものです。
国の生活困窮者自立支援法は、生活困窮者や社会的孤立者を伴走しながら自立にむけた支援を行う積極面と、半面、生活保護が必要な人まで受給しずらくなるのではという問題も指摘されています。
野洲市の条例は「早期発見」に重きを起き、自立支援につながていこうというものです。こうした動きが、国の施策の拡充につながるといいですね。
京都新聞記事 ⇒ http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20160202000024